管理者が知っておきたい労働基準法
医療機関の労務管理に必要かつ不可欠な労働基準法の基礎知識をわかりやすく解説します
労働基準法とは
まず、そもそも労働基準法とはどういう法律でしょうか?
労働基準法は、労働者の方が、働く上での労働条件の原則や決定についての最低限の基準を定めた法律で、労働者保護の観点から作られています。
この最低基準については罰則と行政監督つきで設定されています。罰則とはつまり、例えば法定労働時間の定めに違反した場合は、「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」といった規定があるということです。また、法律を順守させるための行政監督は、労働基準監督署が行います。
次に、この労働基準法を理由として、労働条件を引き下げることは許されません。例えば、施設が昔から労働基準法を上回る労働条件で働かせていたのに、「いや、労働基準法ではこうなっているから」という理由で、あえて労働条件を引き下げてしまうような場合が該当します。
では、逆に労働基準法の定める基準を下回るような労働条件で雇用契約を結んだり、就業規則に規定を設けたりしたらどうなるのでしょうか? 例えば、1年以上勤務しなければ有給休暇は与えないとか、新人は勉強させていただく立場だから残業申請はできないとか・・・。こういった労働条件は無効となり、その場合は、労働基準法の基準の内容が自動的に適用されることになります。
法定労働時間とは
労働基準法では、「法定労働時間」というものが定められています。法定労働時間は、休憩時間を除いて、原則として1日8時間、一週間では40時間と決まっています。ただし、医療機関の場合、職員が9名以下であれば、一週間の法定労働時間は44時間となります。
法定労働時間とは、この時間を超えて労働させることができない時間を言います。これに対して、所定労働時間という言葉があります。
所定労働時間は、皆さんの施設がそれぞれ独自に定めることのできる労働時間のことです。この所定労働時間については、あくまで法定労働時間の範囲内でなければいけませんよ、ということです。
でも、皆さんの業界では、2交代制など1日14時間とか、16時間といった所定労働時間を定める場合がありますよね。これは、のちほどご説明する「変形労働時間制」を採用している場合に限られます。
そして、もう一点。法定労働時間を超えて労働させることはできないと言いましたが、現実に皆さん、法定労働時間を超えて残業されていると思います。実はこれも、36(サブロク)協定というものが締結・届出されていることが前提となります。この36協定についても、のちほどご説明します。
法定休日とは
次に、労働基準法では、休日についても定めがあります。
法定休日として、原則、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。ただし、例外的に、4週間で4日以上の休日を与えることでもOKとされています。
この法定休日は、原則として暦日、つまり午前0時~午後12時の休業をいいます。つまり、夜勤明けの日は、たとえ次の勤務まで24時間空いていたとしても、法定休日を与えたことにはならないので注意が必要です。
なお、法定休日に労働させる場合も、時間外労働と同様、36協定が必要となります。
休憩とは
労働時間が6時間を超える場合には、少なくとも45分以上、労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間以上の休憩を、労働時間の途中に与えなければなりません。
皆さんの業界では、なかなかまとまった休憩が取れないこともあるかもしれませんが、分割してでも、少なくとも法定の休憩時間は確保しなければなりません。
また、基本原則として、休憩中は労働から解放されていること、そして、労働者の自由に利用させなければならない、いうこともあります。
施設によっては、休憩時間中の外出に制限をかけている場合もありますが、施設内で自由に休息できるのであれば、必ずしも違法にはならないという行政通達が出されています。(参考:昭和23年10月30日 基発1575号)
変形労働時間制とは
法定労働時間の説明で出てきましたが、2交代制などのように、8時間を超えて所定労働時間を定める必要があるときは、労働基準法上、「変形労働時間制」の採用が必要となります。
変形労働時間制には、1年単位の変形労働時間制や、1か月単位の変形労働時間制などがありますが、1か月や4週間サイクルで勤務シフトを組むことが多い医療機関で採用されているのは、基本的に1か月単位の変形労働時間制であるといっても過言ではないと思います。
そこで、1か月単位の変形労働時間にしぼってご説明します。考え方としては、あらかじめ労使協定や就業規則へ規定しておけば、1か月以内の一定期間を平均して週40時間以内、ただし職員9人以下であれば44時間以内になるように勤務シフトを組むことにより、日や週によって法定労働時間を超える所定労働時間を定めることが可能になる、というものです。
そうは言っても、1か月以内の一定期間をいちいち平均して週当たりの時間をチェックするのは面倒なので、実務上は次のように考えます。
たとえば、4週間でシフトを組む場合、所定労働時間が合計160時間以内になるようにシフトを組めば、平均したときに1週当たり40時間以内となります。同じ考え方で30日であれば171.4時間以内、31日であれば177.1時間以内。この時間内でシフトを組めば、1日12時間とか、1週45時間といった、一見、法定労働時間を超える所定労働時間があったとしても、平均すれば週40時間以内になるのでOKという考え方になります。
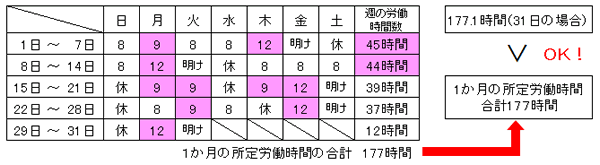
なお、9人以下で週44時間であれば、4週の場合は176時間以内、30日であれば188.5時間以内、31日であれば194.8時間以内です。
※1か月単位変形制の上限時間=40(44)時間×変形期間の暦日数/7日
36協定とは
法定労働時間外や法定休日に働かせるには、あらかじめ「時間外労働・休日労働に関する労使協定」というものを締結して、所轄の労働基準監督署へ届出しておく必要があります。そうしなければ「労働基準法違反」、ということになってしまいます。
この「時間外労働・休日労働に関する労使協定」ですが、労働基準法第36条に定められていることから、俗にサブロク協定という言い方をしています。
なお、サブロク協定さえ結べば何時間でも延長できるかと言えばそうではなく、36条では「限度時間」を超えない時間に限るとして、1か月なら45時間まで、年間なら360時間までと定めています。
なお、業務の都合上、臨時的にどうしてもこの限度時間をも超えてしまう場合があるときは、「特別条項」というものを締結することにより、この限度時間を超える延長時間を設定することも可能です 。
年次有給休暇について①
皆さんのお仕事は、なかなか年次有給休暇がとれない業種かもしれませんが、法律上の要件は、入職して6か月間勤務して、その出勤率が8割以上であれば、原則10日の年次有給休暇が付与されることになります。そして、勤務時間や勤務日数に応じて、この表のように付与日数が決まっています。
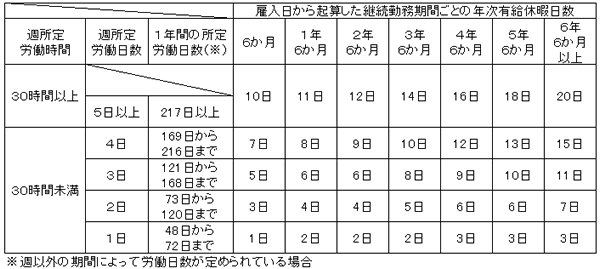
例えば、週の所定労働時間が30時間以上であれば、所定労働日数に関係なく10日が付与されます。30時間未満であれば、週所定労働日数により、また、週以外の期間によって労働日数が定められている場合は年間の所定労働日数により、付与日数が決まります。
週所定労働日数が1日であっても年次有給休暇は発生しますので、パートだから年次有給休暇はない、という概念はありませんのでご注意ください。
なお、年次有給休暇は勤務年数により徐々に増えていき、一般に6年6か月以上の勤務で20日の付与となります。年次有給休暇の権利は、2年使わなかったら時効で消えてしまいますが、逆に言えば、20日付与されている方が1年間使わなかったら、更にプラス20日で、最大40日の有休を保有することになりますので、違う意味で注意が必要です。
年次有給休暇について②
年次有給休暇のポイントについていくつかご説明します。
まず、年次有給休暇は、「承認」や「許可」により与えるという性格のものではなく、本来、労働者が年次有給休暇を取得したい日に、無条件で与えられるものであるということです。このあたりが、年次有給休暇に関するトラブルのもとになりやすいところです。
では、労働者から請求されたら、いかなる場合でも与えなければならないのでしょうか?
例えば、ある病棟で、皆が同じ日に取得したいと言ってきたら?
年次有給休暇を取得させることにより、事業の正常な運営を妨げることとなる場合には、使用者は、労働者に対して別の日に取得するように求める権利が認められています。これを「時季変更権」と言います。
ただし、この「事業の正常な運営を妨げる場合」について、過去の裁判例では事業の規模、内容、その労働者の担当する作業内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行等諸般の事情を考慮して客観的に判断すべきとしています。ですから、単に「人手が足りないから」とか、「忙しいから」という理由では安易に行使できないので注意が必要です。
年次有給休暇について③
次に、年次有給休暇は、暦日単位の付与が原則となります。つまり、先ほどの法定休日と同じく、午前0時~午後12時ということです。ただし、半日単位で与えることも、本人が希望して、なおかつ使用者が同意した場合はOKとなっています。
そして労使協定を結べば、時間単位で与えることも可能となります。ただし、付与された日数すべてを時間単位で取れるわけではなくて、あくまで5日分を限度として、ということになります。
また、労使協定を結べば、年次有給休暇のうち5日を超える分について、勤務編成の際など、使用者が一方的に休暇取得日を割り振ることができます。これを「年次有給休暇の計画的付与制度」といいます。5日を超える分というのは、少なくとも5日分は本人が取りたいときのために残しておいてください、ということです。本来、年次有給休暇は労働者本人が取りたいときに取るものですが、勤務シフトも踏まえて、より効率的に取得してほしい場合に有効なやり方です。
逆に言えば、労使協定もないのに、勤務編成の際に勝手に休暇取得日を割り振ってしまうと、かえってトラブルになるのでご注意下さい。
年次有給休暇について④
これまで年次有給休暇は、本人が取得したいと言わなければ、結果的に取得ゼロでも使用者が法違反に問われることはありませんでした。
そのため、人員不足の医療機関では、そもそも取得を言い出しにくい職場雰囲気であったり、取れなくて当たり前という諦めムードから、ほとんど誰も取得しないこともあり得たと思います。
しかし、2019年4月から年次有給休暇取得のルールについて大きく変わりました。労働基準法改正による「年次有給休暇の5日取得義務」の導入です。
具体的には、使用者が労働者に対し、5日については1年のうちに時季を指定して与えなければならないことになりました。
まず、対象となる労働者は、年次有給休暇が10日以上付与されている方です。(繰り越し分は含めません)
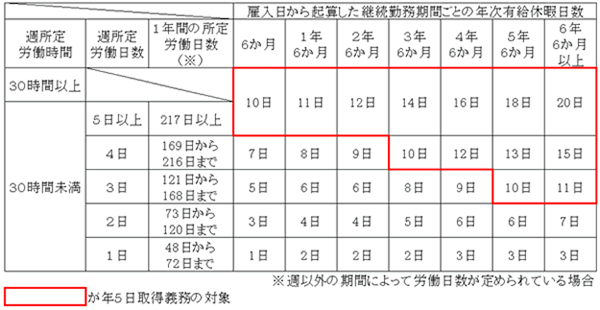
つまり正職員に限らず、週4日とか3日勤務のパートの方であっても、勤務年数によっては対象となるということです。
次に、いつからいつまでに5日取得させるか? これは2019年4月1日以降、労働者ごとに有休が付与された日(「基準日」と言います)を起点として、次の基準日までの1年間です。これがその後1年経過するごとに繰り返されます。
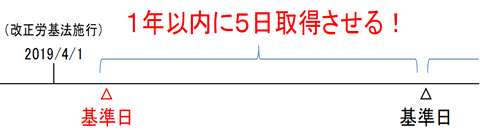
時季指定の方法としては、使用者が労働者に取得時季の意見を任意の方法で聴取し、その意見を尊重した上で、時季を指定して取得させることになります。(尊重なので、努力した結果、希望に添えないこともあり得ます)
なお、使用者の時季指定については、時季指定の対象となる労働者の範囲・時季指定の方法等について就業規則に記載しておかなければならない、そうしないと労働基準法違反(ひどい!)とされているので要注意です。
この5日については、本人の時季指定や計画的付与により取得された日数分については指定の必要はありません。要するに使用者の時季指定、労働者側からの請求&取得、労使協定による計画年休、どの方法でもいいから年5日取得させればOKということです。
振替休日と代休について
次に、振替休日と代休についてご説明します。
労働基準法でいう振替休日とは、あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とするものです。例えば、休日である日曜日を勤務日に変更する代わりに、もともとの勤務日である水曜日を休日とするように、休日と他の勤務日をあらかじめ使用者が指定して振り替えることをいいます。このあらかじめ、というのがポイントになります。
これに対して代休は、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休日とするものです。要するに、休日の振替手続きをとらず、本来の休日に労働を行わせた後に、その代わりの休日を付与することをいいます。この休日は、使用者が指定することもあるし、労働者の申請によって与えることもあります。
大きな違いは、割増賃金が発生するかどうかです。振替休日の場合、振り替えた休日が同一週内の場合、休日出勤日には割増なしで通常の賃金を支払えばよく、振替休日に賃金を払う必要はありません。これに対して代休は、休日出勤日に割増賃金を支払わなければなりません。休日に出勤して労働した、という事実が残るからです。
こう言うと、振替休日の方が使用者にとって有利に聞こえますが、振替休日にはいくつかの要件があります。まず、そもそも就業規則などに振替休日が規定されていなければなりません。その上で、振り替える休日があらかじめ特定されているということ、その振替休日は所定の4週間以内の日でなければならないということ、そして、振替は前日までに本人に予告されなければならないということです。
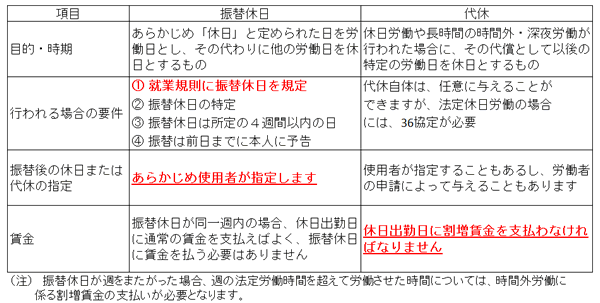
イメージとしては、こんな感じです。
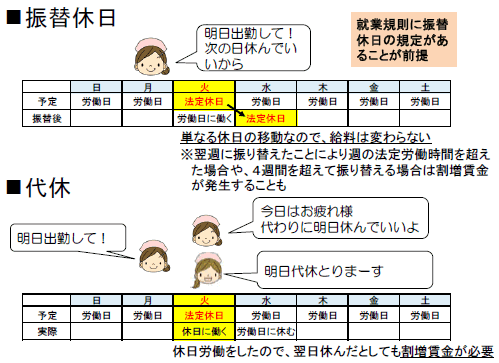
よく、実態は代休なのに賃金に関してだけ振替休日のように扱われている場合がありますが、要件などを踏まえてきちんと運用しないと、トラブルの元となりますので注意が必要です。
宿日直勤務について
医療機関では、「当直」や「宿直」という言葉や、その運用が混同していることがあります。ここでは、労働基準法でいうところの「宿日直勤務」について説明します。
労働基準法では、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、労働基準監督署長の許可を受けた場合は、労働時間等に関する適用を受けることなく使用することができるとされています。
つまり、宿日直勤務については、「労働時間としてはカウントされない」ということなので、許可にあたっては、具体的な基準を定められています。
(一般的許可基準)
1 勤務の態様
・常態としてほとんど労働する必要のない勤務
・原則として、通常の労働の継続は許可しない
2 宿日直手当
・1日又は1回につき、宿日直勤務を行う者に支払われる賃金の1日平均額の1/3以上
3 宿日直の回数
・宿直については週1回、日直については月1回を限度
4 その他
・宿直については、相当の睡眠設備の設置が条件
上記に加えて、医師、看護師等の宿直については、長い間「医師、看護婦等の宿直勤務について」(昭24.3.22基発352号)で許可基準の細目が示されてきましたが、令和元年7月1日に「医師、看護師等の宿日直許可基準について」(基発0701第8号)が新たに示されました。
主な内容は以下の通りです。※例示については看護職員について抜粋
「医師、看護師等の宿日直許可基準について」
1 次に掲げる条件の全てを満たし、かつ宿直の場合は夜間に充分睡眠がとりうること。
(1) 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。
(2) 宿日直中に従事する業務は、一般の宿日直業務以外には、特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限ること。例えば次に掲げる業務等をいう。
・看護職員が、外来患者の来院が通常想定されない休日・夜間(例えば非輪番日であるなど)において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動に対応するため、問診等を行うことや、医師に対する報告を行うこと
・看護職員が、病室の定時巡回、患者の状態の変動の医師への報告、少数の要注意患者の定時検脈、検温を行うこと
(3) 一般の宿日直の許可条件を満たしていること
2 宿日直の許可が与えられた場合、宿日直中に、通常の勤務時間と同態様の業務に従事すること(看護師等が医師にあらかじめ指示された処置を行うこと等)が稀にあったときについては、一般的にみて、常態としてほとんど労働することがない勤務であり、かつ宿直の場合は、夜間に十分な睡眠が取り得るものである限り、宿日直の許可を取り消す必要はないこと。また、当該通常の勤務時間と同態様の業務に従事する時間については労働基準法第33 条、第36条による時間外労働の手続を行い、同法第37条の割増賃金が支払われること。
3 宿日直の許可は一つの病院、診療所等において、所属診療科、職種、時間帯、業務の種類等を限って与えることができるものであること。
ポイントは、まず、今の当直勤務等が「労働基準監督署長の許可」を受けたものであるかということ。もし、受けていなければ、休憩時間を除き労働時間として扱われていなければなりません。つまり、賃金の扱いも通常通り。深夜割増賃金はもちろん、場合によっては時間外割増賃金も発生するということです。
次に、もし、「許可」を受けたものであったとしても、それが上記の基準に照らして正しく運用されているかどうかです。突発的な対応は(その時間に関して労働時間として扱われる限り)仕方ないとしても、慢性的な人手不足等により、通常の夜勤勤務と大して変わらないことが常態であれば、それは大きな問題であり、許可を取り消される可能性もあります。
管理監督者(労働時間、休憩、休日の適用除外)について
労働時間、休憩、休日について、実はこれらが適用されない労働者がいます。適用されないというのは、単に法定労働時間に関係なく長時間働かせていいとか、休憩や休日を与えなくてもいいということではなく、実際の勤務が、通常の労働者と同じような規制になじまないから、という趣旨です。
①農業又は水産業等の事業に従事する者
②管理監督者、機密の事務を取り扱う者(管理監督者イコール管理職でないことに注意!)
③監視又は断続的労働に従事する者※
④宿日直勤務者※
※労働基準監督署長の許可が必要
医療従事者で関係があるのは、②と④でしょうか。④は、前項で説明した通りです。ここでは、②の管理監督者についてご説明します。
みなさん、「名ばかり管理職問題」という言葉がご記憶にないでしょうか? かつて大手ファストフードチェーンの店長などが裁判を起こした事案をきっかけに、急速に広まった言葉です。管理職とは名ばかりで、ただひたすら長時間労働に追われ、その一方で労働時間の適用除外だからとして、残業代はまったく支払われない。これは、おかしい。実態は一般労働者と変わらないではないか、という問題提起でした。
実は、法律で適用除外となっている管理監督者とは、労働基準法第41条でいうところの「監督又は管理の地位にある者」のことを指しています。この定義は結構厳しく、まず、経営者と一体的な立場と呼ぶにふさわしい重要な職務内容、責任があることとなっており、それに見合う権限の付与が行われていることが前提となります。次に、重要な職務と責任を有していることから、現実の勤務が実労働時間の規制になじまないようなものとなっているかということ。さらに、給与やボーナスなどについてもその地位にふさわしい待遇がなされているか、といったことが示されています。
少なくとも、科長や師長などに昇進して管理職になったから、残業代が出なくて当たり前、という単純な話ではないということです。
また、管理監督者であっても、深夜業の適用はあります。深夜業(原則夜10時から翌朝5時までの時間帯の労働)の適用とは、深夜労働に対しては割増賃金が支払われなければならないということであり、妊産婦が請求した場合は深夜業が禁止になるということです。